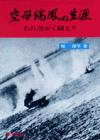ネイヴィーアラカルト
Top Gun (トップ・ガン)と日本海軍戦闘機の格闘技“ひねりこみ”

故 阿部 三郎(元零戦搭乗員・海軍中尉)
今では少々古い話になるが、アメリカ映画で、TOP・GUNというアメリカ海軍戦闘機の物語があったことを、まだ記憶している人があるだろうか。
当時の人気俳優トム・クルーズを主役にした、米海軍戦闘機乗りのエースを選りすぐり、べトナム戦争で苦杯をなめた戦闘機の戦闘方法をやり直そうとするエリート学校の物語である。
映画館は、大半が若い女性で占められ、およそ戦争や戦闘機隊の訓練風景等とは似つかわしくない雰囲気である。
腹に応えるジェット機の轟音と、航空母艦からカタパルトで射出される見るからに重量感溢れるF-14の発艦から始まった。
ミサイルに頼っていたベトナム戦線の苦戦から、戦闘機本来の格闘戦、いわゆるドッグファイトの再検討と新戦法の研究開発が、選りすぐりのパイロットの課題であり、この訓練学校の使命でもあった。
誰が卒業時にトップの成績を取るかで、毎日しのぎを削る激しい競争がくり返される。
ある日、仲間の1機に追い詰められたパイロットが、不意にエンジンを絞ってスピードを落とし、敵機をつんのめらしてやり過ごし、後ろに回り込んで撃墜するという場面があった。これが、演習後の講評で新しい戦法として大変賞賛された。これが映画のストーリーであった。
実は、この戦法は、かって日本海軍の戦闘機が日支事変の時に使ったことがあり、それなりの戦果をあげたが、スピードを落とすことは第三の敵機に対して危険であるという理由で、戦法としては採用されなかったという経緯がある。
そしてその後、海軍の戦闘機乗りは、エンジンを絞らず「ひねりこみ」という斜め宙返りに横滑りを加 えた特殊の三次元の操縦法で、敵機をつんのめらして撃墜するというすばらしい戦法を編み出し、零戦を世界無敵の戦闘機として、歴史に名を残させることに成功した。
アメリカともあろう国が、こんな陳腐なことを、今さら映画とは言え、新戦法として取り上げるはずもないと思うが、いささか、かっての日本海軍の戦闘機乗りとしては、その猛訓練と練度の高さを、50年ぶりに再確認した一夕であった。
源田実と柴田武雄の終生の輪争
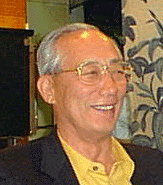
故 阿部 三郎(元零戦搭乗員・海軍中尉)
日本が太平洋戦争に敗れて50年以上たった現在、緒戦で圧倒的な戦果を収め、米軍パイロットを恐怖のどん底に陥れた零戦(レイせん)はなおも語り継がれ、その性能とパイロットの技量に疑間を差し挟む人は少ない。
しかし、この通称ゼロ戦の性能とその用兵について、設計段階から激しい対立があり、戦中、戦後も論争が続き、当事者の死をもって一応の終止符がうたれたことは余り知られていない。
その当事者とは、源田実と柴田武雄である。二人は海軍兵学校の同期生で同じ戦闘機搭乗員を目指した。
12試艦戦(ゼロ戦の試作機の名称)設計のあまりに過酷な要求項目に苦慮した設計責任者の三菱掘越次郎氏は、会議の席上でその項目に優先順位をつけてほしいと申し出た。
空戦性能と速力と航続力の3点はそれぞれ相反する要素である。空戦性能を最重点にすれぱ、速力はある程度犠牲になり、また航続力も影響をうける。また、速力に重点を置けぱ、空戦性能は制約されてしまうし、燃科を沢山積めぱ速力は落ちてしまう。
当時パイロットを代表する源田と柴田は激しく論争した。
源田は空戦性能最優先を唱えた。当時、彼は源田サ-カスの異名をとるほどの編隊空戦の立て役者であった。これに反して柴田は、速力重視を主張した。スピ-ドが劣れば、敵に逃げられてしまう。空戦性能の低下は、パイロットの技量向上で補えると唱え、両者は譲らなかった。 読者はどう判断するだろうか?
堀越技師以下の設計陣は、両者の主張を何とか満足させたいと、苦心の設計に挑み、世界の想像を絶する高性能の戦闘機を開発した。
僅か940馬力のエンジンで最高時遠533キロメートル、当時どこの国の戦闘機も搭載できなかった20ミリ機銃2丁と7.7ミリ機銃2丁を装備し、爆弾 も60キログラムを2発積むことが出来、増槽をつければ長駆3,350キロメートルを飛び続ける戦闘機を創り上げたのである。開戦の日、台湾の高雄からフィリピンのクラーク・フイールド基地に空襲をかけたゼロ戦を、アメリカは戦後まで航空母艦を使って空襲したと思いこんでいたことでもその優秀さが分かる。
しかし、この防御装置を犠牲にして創られた脅威の戦闘機も、やがて戦況が互角になり、消耗戦の様相を帯びてからは、その弱点が被害を加速度的に増大させ る。また、柴田武雄の主張がとおっていたら、グラマンはそう簡単にダイブで左にひねりながら逃げられなかったろうし、逆に追われた時も敵を引き離して脱出 することが出来ただろう。
派手な機動部隊の陰で、柴田等の基地航空部隊は、黙々と航空撃滅戦を展開していた。連日休みのない戦闘を、限られた搭乗員と機材とで黙々と繰り返しなが ら、次々と南瞑に消えていった。そんな基地航空部隊を率いた柴田には、零戦の設計段階での自分の主張が通らなかった無念さが戦後も尾を引いていて、事ごと に源田と論争を繰り返し、ついにはお互いに口もきかず、手紙で論争を繰り返していたと言う。
源田も柴田も掘越ももうこの世にはいない。